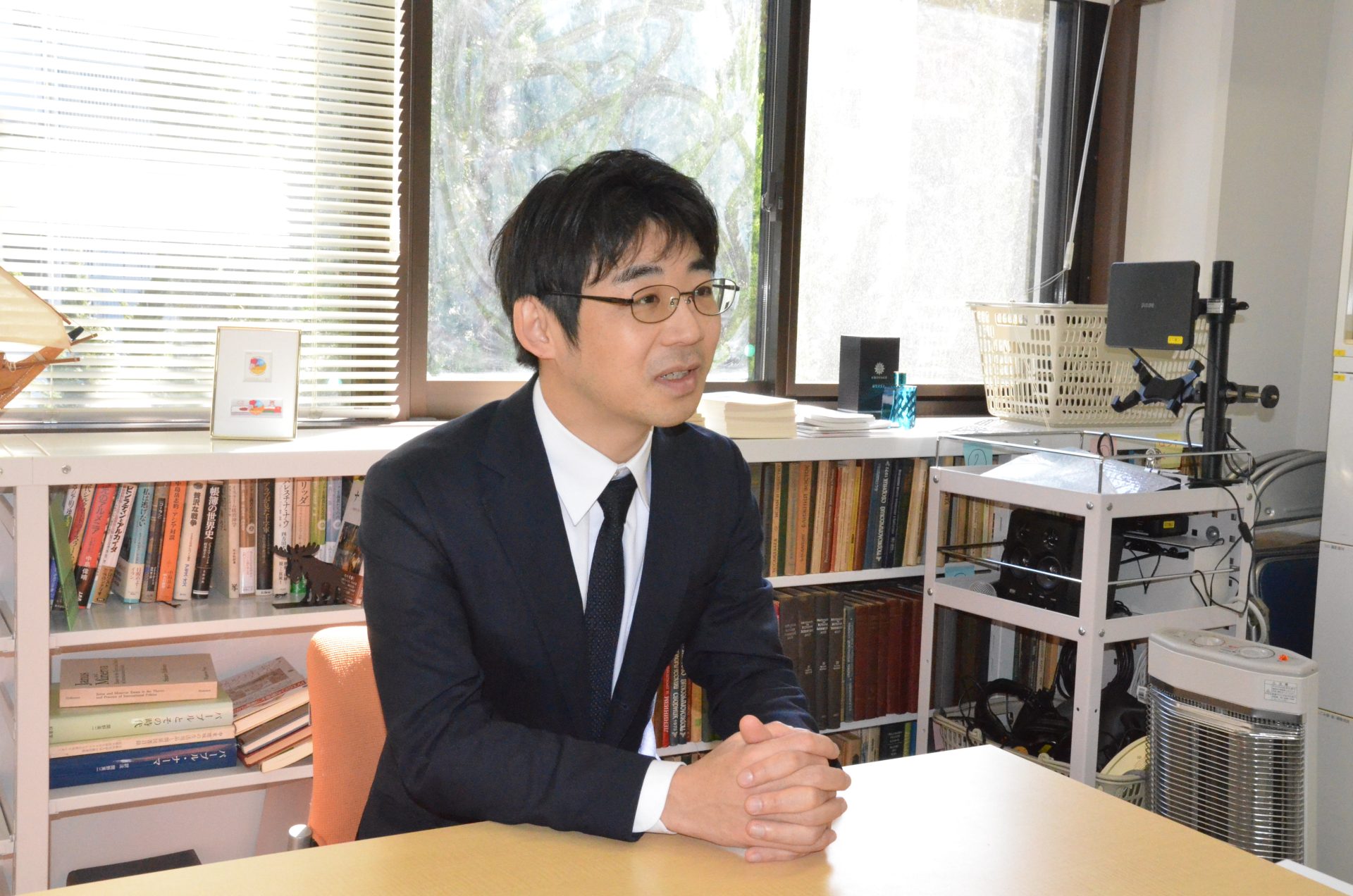2024年11月5日、米国で大統領選挙が実施され、共和党の候補者ドナルド・トランプ氏が当選を果たした。2025年1月20日には、2期目のトランプ政権が始動することになる。その準備として次期政権で要職を担う陣容が徐々に明らかにされ、米国の対外政策の輪郭も浮かび上がってきた。
次期政権の動向の中でも、対外政策を巡るものは世界的な注目を集めている。殊にトランプ政権に関しては、2017年から2021年までの1期目において、同盟国に相応の防衛費負担を求めるなどの動きが見られ、良好な関係を有してきた国々にとっても対米政策を見直す必要性が認識されるようになっていた。
次期トランプ政権の対外政策の方向性は、1期目同様に、軍事的非介入と保護貿易という基本原則を踏まえた「米国第一主義」であるとされる。その考え方をもとに、2024年11月末までに指名された要職の人選を踏まえると、中東政策の特徴をつかむことができる。以下では、この点について、選挙活動中のトランプ氏の発言や変動する現地情勢を交えながら考察してみたい。
選挙戦最中に分断を招いたガザ戦争
2024年の大統領選では、例えば米Gallup社が2024年4〜10月の半年間に1カ月ごとに実施した世論調査によると、経済問題を最大の争点と認識している人が最多であった。それ以外では、移民問題と政府・リーダーシップの問題への関心が高いことが示された。中東問題への対応を含む対外政策の優先順位は高くはなかった。
それでも、2023年10月7日に発生したハマスを中心とするパレスチナ諸組織[1]によるイスラエルへの襲撃事件(以下、10・7事件)が、その数カ月後の大統領選の結果と無関係であったとは言い切れない。例えばミシガン州では、民主党を支持する傾向にあったアラブ系有権者の多くが、共和党候補者であるトランプ氏に投票したとされている。その背景には、バイデン政権が10・7事件に伴い勃発したイスラエルとハマスらとの「ガザ戦争」に対し、イスラエルを支持する言動を繰り返してきたことへの反発と失望があったという。
バイデン政権は、10・7事件を「イスラエルの9・11(9・11=2001年9月11日にイスラム過激派によって起こされた米国同時多発テロ事件)」と呼び、中東への関与を強めていった。ガザ戦争が勃発すると、米国は仲介役の1カ国として、イスラエルとハマスとの停戦実現に向けた間接交渉に関わるようになった。また、10・7事件がイスラエルとイラン、あるいはイラン率いる諸勢力からなる「抵抗の枢軸」との全面衝突の危険性を高めると、イランをけん制するために地中海に空母を派遣するなど軍事的関与も示してきた。
バイデン政権は、発足当初からイスラエル寄りの政策を維持してきた。10・7事件も「イスラエルの9・11」と位置付けることでその政策を正当化してきたが、ガザ住民の被害が拡大する中、政権に対する批判が高まり、国内ではガザ戦争を巡る親イスラエル派と親パレスチナ派の分断が顕在化した。特に米国内の大学では、学生らが親パレスチナ・デモを構内で展開するようになり、停戦の実現を含む「パレスチナの解放」を主張し、イスラエルを支援する企業への投資の引き上げを大学側に求める動きが見られた。2024年4月にはテントで野営しながらデモが行われていたコロンビア大学において、大学側の要請を受けた警察が介入し、学生が逮捕される事態へと至った。米大統領選は、ガザ戦争勃発から1年を迎えてもなお終結のめどが立たない過程と並行して続けられたのであった。
「イスラエルの最善の友人」の豪語
こうした中、トランプ氏は、ガザ戦争を中心とする中東情勢について以下のような発言をしてきた。まず、イスラエルとの関係では、自身を「イスラエルの最善の友人」と位置付け、イスラエルを全面的に支援する立場を明らかにした。その上でトランプ氏は、例えば2024年7月末、米国議会での演説のために訪米していたイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との会談で、自身が大統領選挙に勝利した場合、政権が始動するまでにハマスとの戦争を終えるよう同首相に求めたという。
また、トランプ氏は「自身が大統領であったならば、10・7事件は発生しなかった」という見解も表明してきた。トランプ政権はイランに対し「最大の圧力」政策をとってきたので、イランの支援を受けてきたハマスがイスラエルに攻撃することは不可能だったはずだ、というのがその理屈である。確かに1期目のトランプ政権は、2018年5月にイランと米国を中心とする関係6カ国の間で締結された核合意から離脱し、イランへの経済制裁を強化した。
さらに、トランプ氏が「終わらせる」と豪語したのはガザ戦争だけではない。10・7事件を契機として、イスラエルは、レバノンを拠点とする「抵抗の枢軸」の一組織、ヒズボラとの全面衝突にも突き進むことになった。トランプ氏は、この対立についてもガザ戦争と同様に終わらせる、との立場を明らかにした。ただし、それらの手法に関する詳細について語られることはなかった(編注:11月27日、イスラエルとレバノンによる60日間の停戦合意が発効した)。
2024年10月1日にイランによるイスラエルへの攻撃が発生すると、第1期トランプ政権はイランを完全にけん制できていたとの見解から、自身が大統領であったならば、完全に封じ込められているイランは、それ故に必死に米国と取引しようしたはずだとして、「イランによるイスラエルへの攻撃は発生しなかった」とも述べた。
またトランプ氏は、イランが核兵器を所有することには断固反対する姿勢を示している。バイデン大統領は、上述したイランによる攻撃への報復として、イスラエルがイラン核施設を狙うことは支持しないと述べたが、トランプ氏は、「『核施設を先に攻撃し、心配は後ですればいい』とバイデンは言うべきだった」との趣旨の発言をした。
さらにトランプ氏は、自身が当選すれば、イランと再交渉し、迅速に合意を締結する用意があることを明らかにした。イランが、第1期トランプ政権の外交上の成果であるイスラエルとアラブ諸国(UAE、バーレーンおよびモロッコ)との国交正常化合意(いわゆる「アブラハム合意」)の締約国になる可能性すら示唆した。
親イスラエル路線の人選
一連のトランプ氏の発言を踏まえると、次期トランプ政権の中東政策も親イスラエル的であり、かつイランへの対応を中核とする方向だろう。選挙結果の判明から1週間も経たずして発表され始めた次期トランプ政権の陣容の中で、中東政策に関連すると思われる要職の人選にも、親イスラエルが色濃く反映されている。
まず、次期国連大使として指名されたのが下院共和党会議議長のエリス・ステファニック議員で、イスラエルの支持者とされる。同議員は、2023年12月に行われた下院教育・労働委員会の公聴会で、証人として出席したペンシルベニア大学、ハーバード大学およびマサチューセッツ工科大学の学長たちに対し、「学内で『ユダヤ人のジェノサイド』を呼びかけることが学則違反に該当するか否か」を質し、注目を集めた。というのも、学長たちは、学則違反に当たるか否かは「文脈による」として学内の反ユダヤ発言を非難せず、その姿勢に批判が高まった結果、2023年12月にはペンシルベニア大学のエリザベス・マギル学長が、2024年1月にはハーバード大学のクローディン・ゲイ学長がそれぞれ辞任することになったからだ。
駐イスラエル大使には、バプテストの牧師でもあり元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビー氏(写真)が指名された。宗教的な保守でイスラエルへの巡礼ツアーを主催しており、2008年および2016年には大統領選挙への出馬を表明した人物である。10・7事件の発生以降、イスラエルへの確固たる支持を表明してきたとされている。ハッカビー氏は、「ヨルダン川西岸地区(以下、西岸)」と呼ばれる領域について、「神がユダヤ人に約束された土地である」とのユダヤ人入植者らと同様の立場を有しており、西岸という呼称、占領もしくは入植地といった表現、パレスチナ人の存在のいずれも認めていないという。パレスチナ国家がイスラエルの領土内に樹立されることに反対し、エジプト、シリアもしくはヨルダンといった近隣のアラブ諸国の領域に置かれるべきとの持論を主張してきた。

さらに、中東問題担当の大統領特使には、不動産開発業者でトランプ氏のゴルフ仲間であるスティーヴン・ウィトコフ氏が指名された。ウィトコフ氏の政治的な立場には不明な部分も多いが、トランプ氏への多額の献金を集めた人物であるとされている。トランプ氏には、「イスラエルの最強の同盟相手(Israel’s strongest ally)」と評されている。
「親イスラエル」と「米国第一」の相克も?
ネタニヤフ首相を始めとするイスラエルの閣僚らは、トランプ氏による人選に歓迎の意を表明した。右派・宗教勢力によって構成されるネタニヤフ政権にとっては、自身の政策的立場との親和性の高い顔ぶれが出揃ったことになる。次期駐イスラエル大使の指名を受けたハッカビー氏は、第1期トランプ政権下で達成されたエルサレムに対するイスラエルの首都認定(2017年12月)、在イスラエル米国大使館の開設(2018年5月)、ゴラン高原に対するイスラエルの主権承認(2019年3月)などの一連の政策を評価し、自らにはその路線の踏襲が求められていると発言した。
次期トランプ政権下で親イスラエル的な政策が実施されるのはほぼ確実であるが、不透明な部分も多分に存在する。親イスラエル路線と「米国第一主義」は同時に重視されるであろうから、イスラエル寄りの米政権であっても利害対立が生じないとも限らないためである。
この点、最も懸念されるのは、2025年にイスラエルが西岸を併合する可能性であり、それに対する米政権の反応である。駐イスラエル大使として宗教的保守派のハッカビー氏が指名されたことは、米国が併合に前向きであることを示唆している。だが、トランプ氏がイスラエルによる西岸の併合を認めないのではないかとの見通しが、トランプ氏に近い共和党の上院議員の発言としてイスラエル紙で報じられている。トランプ氏は、サウジアラビアを「アブラハム合意」に引き込みたいとしており、既に共和党のリンゼイ・グラハム上院議員がサウジアラビアとイスラエルとの国交正常化に向けて動いているという。西岸併合は、イスラエルに対するサウジアラビアの態度を硬化させ、両国間の国交正常化の妨げとなることから、トランプ氏が難色を示しているとされている。
トランプ氏が「アブラハム合意」の次期締約国としてサウジアラビアに狙いを定めるのは、まず、イスラエルとスンニ派アラブ諸国との協力関係を促進し、シーア派であるイランに対する包囲網の形成を意図することで、岩盤支持層・キリスト教福音派の支持を固められるからである。また、「アブラハム合意」を拡大し、サウジアラビアを「米国圏」にとどめられれば、サウジアラビアが中国やイランに接近することを防ぐ可能性も高まる。
10・7事件は、トランプ政権の1期目において後景に退いていたパレスチナ問題を、アラブ世界における最重要課題として再浮上させた。サウジアラビアにとっては、パレスチナ問題の実質的な進展がないままでイスラエルとの関係を改善すれば、自身の統治の正当性が傷付くことになる。この意味で、イスラエルによる西岸の併合は、トランプ氏の優先順位では当面の間、低くならざるを得ないのであろう。
パレスチナ問題の行く末は、依然として米国とイスラエルの出方にかかっている。当事者の一方が不在のまま外堀が埋められてしまう可能性は、1期目のトランプ政権と同様に濃厚である。
写真:AP/アフロ
[1]例えば、以下の記事によるとハマスを含む5つのパレスチナ組織が10・7事件に関与したとされている。Abdelali Ragad, Richard Irvine-Brown, Benedict Garman and Sean Seddon, “How Hamas build a force to attack Israel on 7 October,” BBC, November 28, 2023.
地経学の視点
安全保障面では、トランプ氏が米国第一を唱える前から、すでに米国は内向きだった。「米国は世界の警察官ではない」と述べたバラク・オバマ大統領(当時)は、化学兵器を使用したシリアのバッシャール・アル・アサド政権に、軍事介入が妥当と判断しながら最終的には見送った。バイデン政権も、支援を徐々に拡大しながらも、ウクライナ戦争に直接介入することは避けている。トランプ氏は、西側の盟主としての体面を繕うことにコストをかけるくらいなら、自国の保護・育成に振り向ける、といった米国の「本音」を素直に表現しているだけなのかもしれない。
しかし、いまだ世界最強の軍事力を持つ米国が、ガザ情勢に強い関心を向けてこなかったことが「10・7事件」の遠因ではないか。バイデン政権で安全保障政策を担当するジェイク・サリバン大統領補佐官が「今、中東は最も静かだ」と述べたのは、事件が起きる8日前のことだった。筆者が指摘するように、パレスチナ抜きでパレスチナ問題の「解決」を図ったところで、次の10・7事件を生むだけだ。
世界を見渡せば、民主主義国は少数派だ。権威主義的な中国は、西側とは異なる価値観で米国と覇を競うまでに成長した。民主主義が世界から値踏みされる中で、米国が殻に閉じこもれば、世界はより不安定化する。バイデン政権下でイスラエルとレバノンが停戦合意したのは一条の光明だが、イスラエルとヒズボラとの小規模な衝突は続いている。停戦を恒久措置とし、ガザ戦争の終結に結び付けられるかは、トランプ次期政権の宿題となる。(編集部)