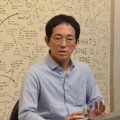2023年以降、中国で「日本化」が話題となっている。2021年夏場から続く不動産不況とその後の低インフレが、1990年代のバブル崩壊後の日本を彷彿(ほうふつ)とさせるためであろう。ただし、「日本化」には2つの見方がある点に注意が必要である。
第一に、「日本化」をバブル崩壊とその後の金融危機への波及と捉える見方がある。日本では、1990年代前半に株価や地価といった資産価格が急落し、バブル崩壊後、金融機関は貸出先の倒産などによる不良債権の急増でバランスシートが悪化した。これにより、金融機関は貸出に過度に慎重となり、金融システムの機能不全が問題となった。その後、1990年代後半には北海道拓殖銀行や山一証券など大手金融機関の破綻や廃業が相次ぎ、金融危機に発展した。
第二に、金融危機には至らないものの、低インフレ・低成長に陥り、中国も日本のような「失われた数十年」を経験するだろうとの見方がある。日本ではバブル崩壊後、CPI(消費者物価)上昇率が急速に低下し、1994年7月に前年比マイナスを記録した後、消費増税時や原油高騰時を除き、CPI上昇率が2%を上回ることはなかった。2001年3月の内閣府『月例経済報告』で、政府が初めて日本経済がデフレに陥っているとの認識を公式に示したが、足元でCPI上昇率2%超えが続く中でもいまだデフレ脱却宣言は出されていない。
実質GDP成長率もこの間、低迷した。第1次オイルショック以来、約20年ぶりの低成長となった1992年度から新型コロナウイルス禍直前の2019年度までの28年間の平均成長率は0.8%にとどまり、世界第2位だった名目GDPは、2010年に中国に追い越され、2023年にはドイツにも抜かれ、4位に転落した。
「失われた数十年」に陥るリスクは大きい
中国の場合、「日本化」の第一の視点である金融危機は十分回避可能だと考えられる(ただし、リスクシナリオもある点については後述する)。その最大の要因として、中国の金融当局は日本の事例を教訓に、金融機関に厚めのバッファー(緩衝材)を確保させていることが挙げられる。2023年の中国の銀行セクターの当期純利益は2.4兆元あり、貸倒引当金の6.6兆元を加えると、損失を吸収するためのリスクバッファーは9.0兆元に達している。それに対し、同年の不良債権額は3.2兆元であり、やや範囲を広げて要注意先への貸出4.5兆元を加えた広義の不良債権も7.7兆元に過ぎず、リスクバッファーで十分にカバーされている。
また、中国では、銀行貸出に占める不動産業向けの割合が低位に抑えられている。バブル期の日本では同割合が12%前後に上ったのに対し、中国では2024年6月末時点で5.5%と、銀行の貸出先が多様化している。
さらに、政府は融資に適した不動産プロジェクトをホワイトリスト(優良案件)に登録し、銀行に対して優先的に融資を実行するよう働きかけるなど、不動産開発企業の資金繰り支援策を強化している。従って、不動産業界で破産が相次ぎ、銀行が多額の不良債権を抱えるシナリオは考えにくい。
一方、「日本化」の第二の視点である「失われた数十年」のごとく、中国で今後、低インフレ・低成長が定着する可能性は高い。足元で、中国のCPI上昇率はゼロ近傍で推移している(図1)。また、経済全体の物価動向を示すGDPデフレーターも、2023年4〜6月期以降、直近2024年7〜9月期にかけてマイナスとなるなど、すでにデフレの兆候が見られる。
【図1】消費者物価とGDPデフレーター(前年比)
消費者物価が低迷する中、企業物価も下落が続いている。工業生産者出荷価格は、2022年10月以降、直近2024年11月にかけて26カ月連続で前年割れとなった。販売価格が下落する中、企業の売上は低迷し、工業企業の税引前当期純利益は2022年、2023年と2年連続で減益となった。2024年も1〜10月累計値の前年同期比が−4.3%となっており、3年連続で減益となる公算が大きい。さらに、企業業績の悪化を受けて、雇用も悪化している。こうしたことから、すでに中国経済は、物価低迷が企業業績の悪化をもたらし、さらに雇用の悪化につながり、個人消費を下押しし、物価低迷の要因となる「デフレスパイラル」に入りかけている。今後、中国の物価が継続的に下落し、本格的にデフレに陥れば、デフレスパイラルが定着するだろう。
供給面に偏る中国の政策
デフレは、マクロ経済の需給バランスが崩れ、需要が供給を下回ることで生じる。中国では、供給過剰と需要不足のいずれも深刻であり、結果としてデフレ懸念が高まっている。特に、家計と企業共に需要不足が目立つ。短期的には、家計において雇用悪化や不動産価格下落による「逆資産効果」により消費者マインドが悪化し、消費を手控える動きが広がっている。企業においては収益悪化により企業マインドが悪化し、投資に及び腰になっている。中長期的にも、人口が2021年をピークに減少へと転じたことで消費・投資の減少は避けられない。また、過去数十年間の投資主導の経済成長により、有力な投資先が減少し、投資効率が下がっていることも、投資を下押しする。
需要面の弱さを主因にデフレおよびデフレスパイラル定着への懸念が高まる中、政府は供給面を強化して経済成長を目指すという考え方にとらわれているように見える。マクロ経済学の用語を用いれば、供給が需要を生み出すという「セイの法則」に従った経済運営がなされているといえる。
もともと中国が採用していた計画経済では、生産=供給をコントロールすることが経済運営の中心であった。最近でも2015年に公表された10年間の製造業発展計画「中国製造2025」や戦略的新興産業の育成・発展を目指した産業政策、2024年の全人代における政府活動報告で打ち出された「新しい質の生産力」の発展方針などは、いずれも先端分野に資源を集中させ、生産力の強化を目指すものである。確かに、供給面の強化は中長期的な経済力の向上につながるが、短期的には国内の過当競争をもたらし、デフレを一段と深刻化させかねない。
一方、需要不足解消のための施策は不十分である。これまで政府が経済対策の中心としてきた産業政策など供給面に働きかける政策は上意下達で進めていくことができたが、需要喚起策は、それぞれの消費者の政策に対する反応が一様でないこともあり、上意下達では大きな効果は期待できない。こうしたことから政府は、ノウハウに乏しい需要喚起策の本格実施に消極的だったが、それでも2024年の全人代直後には耐久消費財の買い替え促進策を打ち出した。同政策は、消費券の配布などを通じ、一定の効果は見られたものの、消費全体を押し上げるには至っていない。また、施策の対象となった自動車や大型家電は耐久年数が長く、一時的な消費券配布は需要の先食いを生むに過ぎないだろう。
こうした供給側に偏ったアンバランスなマクロ経済政策が、デフレを定着させ、デフレスパイラルを一段と深刻にする懸念がある。実際、その歪みはすでに「デフレ輸出」という形で表れている。現在の中国国内の需要規模を無視した供給面の強化が、国内の過剰生産をもたらし、行き場を失った一部の財が海外に向かっている。
そうしたデフレ輸出の典型が鉄鋼だ。リーマンショックが起きた2008年秋、4兆元の大規模経済対策で生産能力を大幅に増強した鉄鋼は、足元の不動産不況で国内鋼材需要が急減したため、過剰生産に陥った。国内で消化しきれない分は輸出に向かい、鋼材の国際市況を押し下げている。
また、電気自動車を含む新エネルギー車(NEV)は、「中国製造2025」における重点産業や戦略的新興産業に指定され、補助金などの政策支援を追い風に、景気減速下でも順調な生産を続けている。上海市党委員会の機関紙である上観新聞で引用された太平洋証券の試算によると、2023年におけるNEV乗用車の中国国内生産能力は1346万台に上った。
一方、同年のNEV乗用車の生産台数は908.7万台と、稼働率は67.5%にとどまり、一般に適正水準とされる80〜90%を大きく下回った。もちろん、各自動車メーカーの海外戦略も考慮する必要があるが、競争の激しい中国市場ではなく海外市場に活路を求めた割安な中国製NEVが、欧州や東南アジア、中南米の市場で存在感を強めている。
こうした状況に危機感を抱いた欧米諸国は、太陽光パネルやリチウムイオン電池などと共にNEVの過剰生産能力を問題視し、2023年末以降、中国への批判を強めてきた。もっとも、欧米をはじめ先進各国は、低廉な人件費に加え、環境コストや人権コストなどが低い[1]中国で生産された廉価な製品を輸入することで、過去数十年にわたり物価を抑制してきた。結果として、先進各国の消費者が大きな恩恵を享受したことも事実である。
その一方で欧米は、中国が補助金など不公正な手段で自国産業を優遇したために、自国の製造業従事者が損害を被ったとの認識も強い。このため、欧米の政府は国内の労働者層に配慮する観点からも、中国に対する批判的な姿勢を強めている。従って、中国が今後、国内のデフレを解消し、デフレ輸出の問題に解決の道筋をつけられなければ、先進各国との関係が一段と悪化する恐れがある。
トランプ関税と金融緩和が高めるリスク
前述したように、中国が金融危機に陥るリスクは当面小さい。ただし、デフレスパイラルが定着し、そこから抜け出せなければ、時間と共に金融危機に発展する可能性が高まる。デフレ不況が長引くと、企業の廃業や倒産が増加し、銀行の不良債権が増え、金融システムへの負荷が増加する。日本の例を見ても、デフレがひとたび定着してしまうと、そこから脱却するのは至難の業である。
そうした中、間もなく米国大統領に就任するドナルド・トランプ氏の対中政策が、中国のデフレを長期化させるリスクがある。トランプ氏は、大統領選挙期間中に中国からの輸入品に対し、一律60%の関税引き上げの方針を示した。大統領選後には、合成麻薬「フェンタニル」の米国への流入に対し、中国政府が十分な対応を講じなければ、中国からの輸入品に対して関税を10%引き上げる旨をSNS上で表明した。仮に実行されれば、中国製品の米国市場における価格競争力が低下し、中国の対米輸出は大幅に減少することが予想される。
2018年以降の米中対立の中で、中国の輸出における対米依存度は低下した。それでも、2023年の対米輸出は輸出全体の約15%を占め、米国は中国にとって最大の輸出相手国である。米国市場向けの製品が関税引き上げにより行き場を失えば、中国国内の供給過剰は一段と深刻化し、物価にも低下圧力がかかる。
また、デフレ定着を避けるための金融緩和の取り組み自体が、銀行セクターの収益環境の悪化をもたらし、金融危機のリスクを高める。現在、中国の銀行は年間2兆〜3兆元の利益を生み出しているが、収益源は貸出金利と預金金利の差である純預貸利ざやである。しかし、金融緩和による貸出金利の引き下げに伴い、純預貸利ざやは縮小傾向にある(図2)。直近2024年9月末時点で、純預貸利ざやは1.53%と、銀行の業界団体である市場金利設定自主機構が設定する警戒ラインの「1.8%」を大きく下回っている。
中国政府は、2024年12月に開催された中央経済工作会議で2025年のマクロ経済運営方針を決定したが、その際、金融政策の方針を昨年までの「穏健」から「適度に緩和」へと表現を変更し、金融緩和を一段と強める姿勢を示した。今後、金融緩和を続けざるを得ない経済状況が長引けば、銀行セクターの体力が徐々に奪われることになるだろう。
【図2】商業銀行の純預貸利ざや(業界平均)
あわせて政府は、中央経済工作会議で、重点政策の筆頭として「消費を促進し、投資効率を引き上げ、全方位で国内需要を拡大する」との方針も示しており、足元の経済状況における内需拡大の重要性は認識しているとみられる。今のところ、抜本的かつ具体的な内需喚起策は示されていないが、中国の金融システムがリスクに対処できているうちに、政府は実体経済を上向かせ、デフレスパイラルから抜け出す必要がある。
仮に、中国で金融危機が発生したとしても、中国では資本移動が制限されていること、中国の対外純資産はドイツ、日本に次ぐ世界第3位であり、対外債務が相対的に少ないことから、リーマンショックのように世界的な金融危機に波及するリスクは大きくない。
それでも、中国は名目GDPで米国に次ぐ世界第2位の地位を占めている上、高成長を続けてきたことで、中国経済は2010年代に、世界のGDP成長率を直接的に毎年1%前後押し上げてきた。貿易を通じて他国の成長率を押し上げるという間接的な効果も加味すると、世界経済への影響力はより大きい。その中国経済がデフレスパイラルで低迷するようであれば、あるいは金融危機の発生で急減速するようであれば、世界経済への影響は大きく、今後の中国経済の動向が注目される。
[1]中国は、欧米に比べて環境保護や強制労働・児童労働禁止などに関するルールが緩く、規制対応に要するコストが少ないということ。
写真:CFoto/アフロ
地経学の視点
中国が日本を抜いて名目GDP世界第2位となったのは2010年。その後、習近平政権が発足したが、大国としての野心に満ちたふるまいとは裏腹に、同政権発足以降の経済成長率(実質GDP成長率)は、コロナ禍からの反動があった時期を除き、下落基調をたどってきた。米国をも抜いて中国がGDP世界一になる時期予測は年々後ろ倒しされ、現在ではその「Xデー」は訪れないという見方も多い。むしろ丸山氏が指摘するように、中国が今後「失われた数十年」を経験する可能性は高い。
日本産水産物の輸入再開の方針やビザ要件の緩和など、このところ日中関係に改善の兆しが見られるのは、中国の苦境のあらわれでもある。国内の不況に加え、第2次トランプ政権が厳しい対中政策をとることに備え、米国に次ぐ貿易相手国である日本との結びつきを強める狙いだ。裏返せば、トランプ氏と習氏の「ディール」が成立すれば、中国にとって日本の重要性は後退し、日中関係が再び冷え込む可能性は否めない。
日本は米国と中国という大国に挟まれ、その地理的制約から逃れることはできない。レアルポリティーク(現実政治)の時代に求められるのは、ある種の権謀術数だ。中国との戦略的互恵関係は堅持しつつ、トランプ氏とのディールの材料として日中関係を「微調整」する——。日本には、そんなしたたかさも必要ではないか。(編集部)